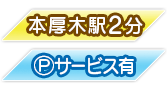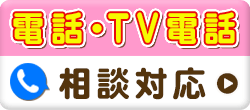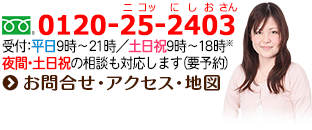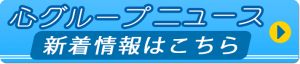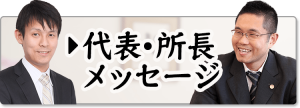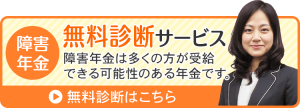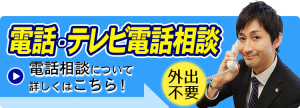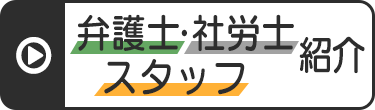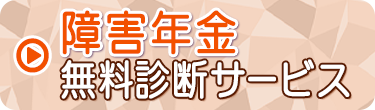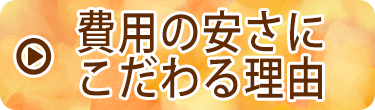精神疾患について障害年金が認められる基準
1 精神疾患についての障害認定基準
精神疾患に関する障害認定基準は、日本年金機構のホームページで公開されています。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
認定基準には、「精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。」と記載されていますが、実際のところ症状としてはどの程度なのかというのは、かなりあいまいな内容といえます。
精神疾患自体、症状に波があったり、発現する症状も人によって様々であったりするため、客観的な基準を示すことが難しいものとはいえますが、過去、障害基礎年金の審査が都道府県単位で行われていた際には、この基準のあいまいさもあって、地域によって認定結果にばらつきがありました。
このような経緯から、精神疾患の等級判定についてガイドラインが策定され、認定基準と合わせて審査の基準となっています。
2 認定基準の区分について
⑴ 精神の障害の認定基準
精神の障害の認定基準をもう少し詳しく見ていくと、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」の6つに区分けされ、それぞれに認定要領が定められています。
⑵ てんかん
このうち、てんかんについては、AからDまでの4つの発作タイプと発作の発生頻度等を参照する基準となっており、ガイドラインの対象外となっていることからも、ほかの5つと比べて別のものと評価してよいかと思います。
⑶ 気分(感情)障害
気分(感情)障害は、うつ病や双極性感情障害等を指します。
そして、認定要領の内容は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害と共通のものとなっています。
⑷ 器質性精神障害
症状性を含む器質性精神障害については、交通事故や脳梗塞、脳出血等によって脳そのものがダメージを受けたことによって発症する精神症状や、認知症、脳腫瘍や神経疾患、内分泌疾患等による精神症状が含まれます。
いわゆる高次脳機能障害もこれに含まれます。
3 ガイドラインについて
⑴ 障害等級の目安について
ガイドラインを見ると、障害等級の目安という表が掲載されています。
これは、精神の障害用の診断書裏面左上の「日常生活能力の判定」欄の7項目について、各項目の4段階評価に応じて程度が軽いほうから1から4として算出した平均値を縦列に、同診断書裏面右上の「日常生活能力の程度」欄の5段階評価を横列にして、日常生活能力の判定の平均値と日常生活能力の評価の組み合わせから、等級の目安を導くものです。
診断書の様式は下記ページをご参照ください。
参考リンク:日本年金機構・精神の障害用の診断書を提出するとき
⑵ 等級の認定は様々な要素を加味して総合的に行われる
ガイドラインでは、⑴の等級の目安に、診断書等の記載内容による様々な考慮すべき要素を加味し、総合的に等級を認定することとされています。
この考慮すべき要素は、ガイドラインで「考慮すべき要素の例」として、①現在の病状又は状態像、②療養状況、③生活環境、④就労状況、⑤その他の5つに分けて、さらに共通事項、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害と気分(感情)障害をまとめた精神障害、知的障害、発達障害という障害の特性ごとに、具体例が示されています。
例えば、④就労状況では、発達障害の場合、仕事内容を考慮するものとされており、一般企業勤務で就労している場合であっても、障害者雇用で周囲の補助等を受けながら単純業務を行っている、といった実態がある場合には、2級の可能性を検討するものとされています。
⑶ 認定の確率
令和2年公表の統計によると、9割以上が目安通りの認定となっていたとされていますが、実際には目安が「2級又は3級」となる案件が多くあると考えられ、この目安で3級(障害基礎年金の場合は不支給)となったものも、統計上、目安通りの認定となっていることに注意が必要です。
また、令和7年、令和6年度の不支給率が前年度の約2倍になったと報道され、その後の厚生労働省の調査で精神障害の不支給率の上昇が大きいと判明する等、ガイドライン等が整備されていても、必ずしも一貫した基準で認定がなされていないことがうかがえます。